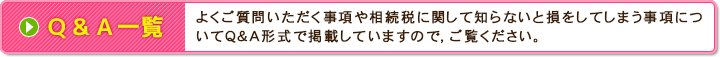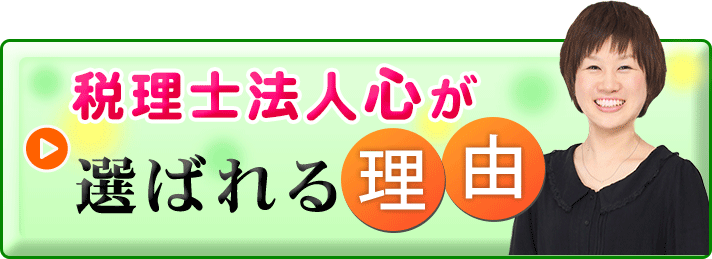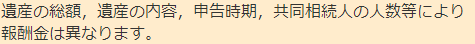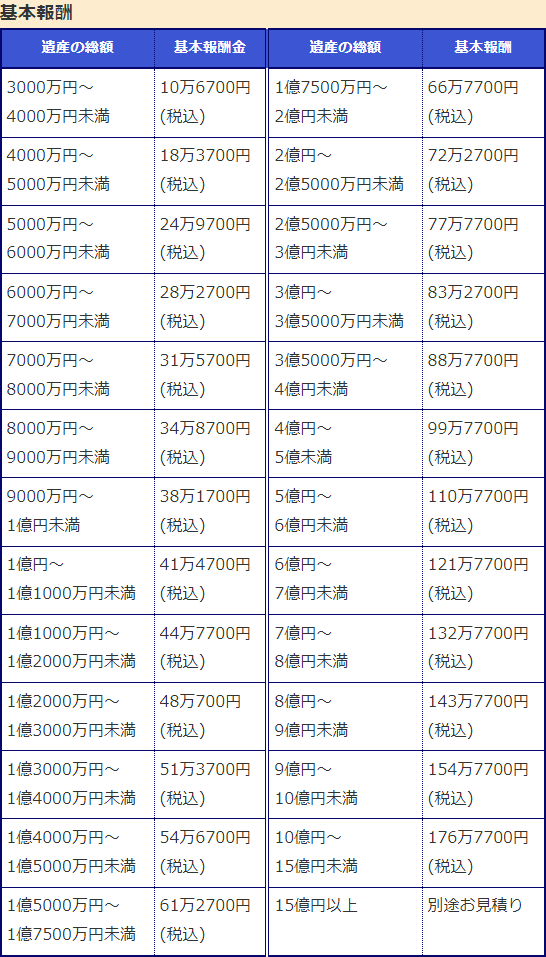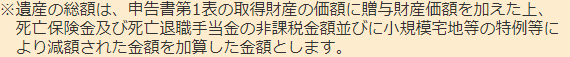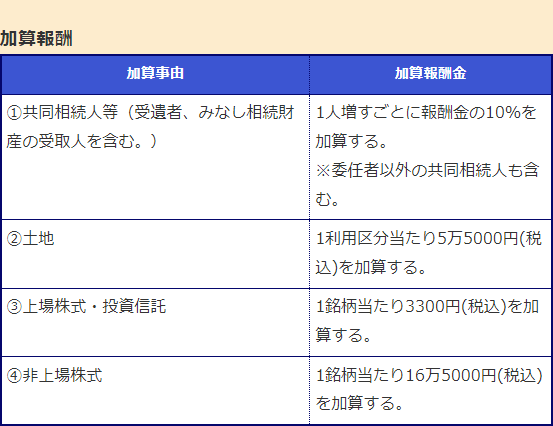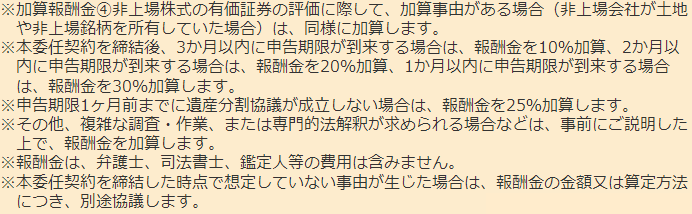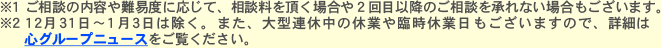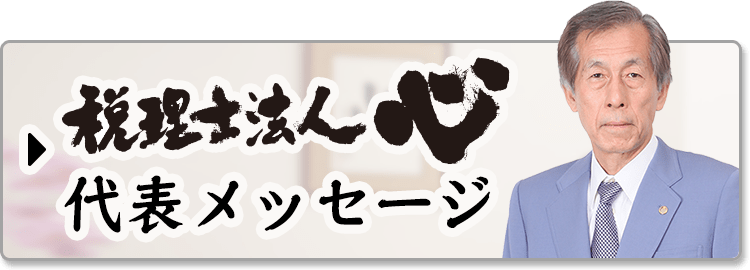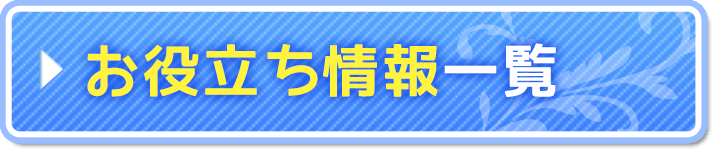お役立ち情報
相続税の路線価を調べる方法
1 路線価を調べる必要があるケース
相続財産の中に宅地がある場合には、宅地の相続税評価額を計算する必要があり、計算方法としては路線価方式と倍率方式があります。
どちらの方式で計算するのかについては、国税庁が公表している財産評価基準書路線価図・評価倍率表から調べることができます。
参考リンク:国税庁・財産評価基準書
このトップページから、都道府県、評価倍率表のうち一般の土地等用、市区町村と選んでいくと、各市区町村の倍率表が出てきます。
この倍率表の中の宅地の列に数字(1.1など)が書かれている場合、倍率方式によって宅地の評価をすることになるため、路線価を調べる必要がありません。
数字ではなく、路線と書かれていた場合には、路線価を調べる必要があります。
2 路線価図の特定
路線価は、先ほどご説明した評価倍率表のすぐ上の路線価図から見ることができます。
トップページから、都道府県、路線価図、自治体と選んでいくと、50音順に並んだ地名が出てきます。
該当の宅地の右側にある5桁の数字のどれかを選ぶと、地図が表示されます。
地図が表示されているページの左側の接続図のところから、八方位で移動できますので、調べたい宅地の場所を探していきます。
3 路線価の調べ方
調べたい宅地の場所の路線価図にたどり着いたら、路線価をみていくことになります。
土地に接している道路上に記載された、数字が丸や四角で囲まれていたり、アルファベットが書かれていたりするものが、路線価にあたります。
単位は千円ですので、例えば500と書かれている場合、路線価は50万円ということになります。
数字の後に書かれているアルファベットは借地権割合ですので、所有権が相続されている場合には使いません。
路線価図における路線価がわかったら、そこから、何路線に面しているのか、間口が狭小・奥行が長大なのか、不整形地なのか、地積規模が大きいのか、無道路地なのか、がけ地などがあるのか、土砂災害特別警戒区域にあるのか、容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地なのか、私道なのかなど、様々な点からの補正を行います。
そして、相続税申告にあたっての路線価を計算し、土地及び土地の上に存する権利の評価明細書を記載していくことになります。